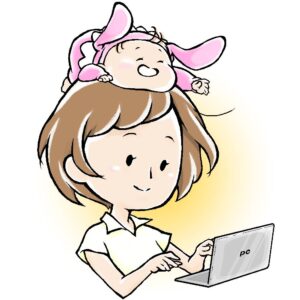普段から飲み慣れているお酒も美味しいけれど、「たまには新しい味に出会いたい」と思っている方も多いのではないでしょうか?そんな時はストーリーでお酒を選ぶのも、ひとつの方法です。
ハイボール派だった筆者が、暖流のソーダ割り(暖ボール)を飲むようになったのは、泡盛と神村酒造のストーリーに心惹かれたから。
今回は、有限会社神村酒造の中里社長(以下:中里さん)に、泡盛と酒造所の歴史についてお伺いしました。琉球王朝時代から、中里さんが泡盛造りに携わるようになった現代まで、タイムマシーンに乗った気持ちでお楽しみください。
小さな島国で貴重な産物だった「泡盛」
沖縄が琉球王国(以下:琉球)と呼ばれていた約600年前に、泡盛は存在したと言われています。資源が乏しい小さな島国だった琉球は、貿易で栄えていました。A国から輸入した商品をB国へ輸出する中継貿易が盛んだったのです。文献を参考に、中里さんが語ってくれました。
「泡盛は常温で保管できる蒸留酒です。おそらく、琉球の先人達が海外で蒸留酒を発見した際、『これなら船で運んでも腐らない。他国に輸出すれば商売になる』と考えたのではないだろうか。そのために、海外から原料を輸入して職人を琉球に招き、蒸留酒である泡盛の製造を始めたのではないかと、歴史を想像しています」
実際、当時泡盛がどれだけ貴重な産物だったかを物語る場所として、首里城の「銭蔵」が挙げられます。琉球王府が金銭を保管する銭蔵で、泡盛も一緒に管理されていたのです。
「職人が造った泡盛を首里城に運び、役人が大切に管理していた。それぐらい、泡盛は琉球にとって貴重な産物だったようです。国を豊かにしていた泡盛造りを、私達は大事に引き継いでいます」
琉球王朝時代から続く泡盛造りの歴史を、中里さんは興味深く語ってくれました。
生き残るためにお酒造りを始めた神村家

泡盛が造られた時代背景を知った上で、神村酒造の歴史に焦点をあてます。
神村家の先祖は、琉球王府に仕えるお役人だったそうです。1879年の琉球処分で琉球王国は沖縄県となりました。その後1882年に、神村家は泡盛造りを始めます。歴代の社長から伝わってきた話を、中里さんはこう語ってくれました。
「例えるなら、公務員の仕事が突然失われるようなものです。大変革の時代、家族や大事な人を守るため、神村家が生き残るために泡盛造りを始めたことは間違いないですね」
創業から時を経て、1945年には沖縄戦が始まり、戦後は原料や資金の不足で満足のいく泡盛造りができない時代を経験します。アメリカ統治下だった当時は、ビールやウイスキーなどのお酒が好まれるようになり、沖縄の泡盛離れが進んだ時期でもありました。
それならば「ウイスキーと泡盛の良さを兼ね備えた商品を造ろう」と、3代目の神村盛英さんが暖流(だんりゅう)を10年がかりで開発。ウイスキー樽で貯蔵・熟成した暖流は、革新的な泡盛として県民に愛されるようになりました。

「1968年に誕生した暖流は、泡盛ではじめて樽貯蔵に挑戦したブランドです。暖流をきっかけに、神村酒造に根付いたチャレンジ精神は現在につながっています」
最近では、「おきなわ県産米泡盛」も製造している神村酒造。一般的に、泡盛はタイ米で造られます。ですが、おきなわ県産米泡盛は、伊是名島で作る泡盛用に改良されたお米を原料とすることで、他商品との差別化を図っていると語ってくれました。
世界には多くの銀行員がいるが、泡盛を広める人はどれだけいるのか?
これまで泡盛と神村酒造の歴史を語ってくれた中里さんですが、20代後半まで、銀行員として地元企業を支える仕事に没頭していたそうです。
中里さんの奥様が神村家の血縁であり、家業に携わっていました。親族とお酒を飲む機会も多く、中里さんも泡盛に関する知識が自然と増えていったと話します。
ある日、お酒の席で銀行の取引先と暖流を飲むことになった中里さん。「美味しいね、この泡盛」と話す取引先の社長に、中里さんは暖流の誕生秘話を熱弁したそうです。
「お世話になっている社長に『昼間の顔より、泡盛を語る今の方が活き活きしているな』と言われてハッとしました。自分には、こんなに熱くなれるものがあるのだと」
その日から中里さんは、泡盛造りに携わりたいという気持ちが強くなっていきます。しかし当時は、銀行の仕事も成果が出始め、転職を迷っていたそうです。転機となったのは、第2子の誕生でした。
「出産に立ち会い、可愛い娘を見た瞬間に迷いは消えました。子ども達が将来悩んだときに、自分はどういう選択をして人生を歩んできたか、堂々と話せるようになろう。そのために、心から熱くなれる仕事をしよう」
1999年、中里さんが28歳のとき、那覇市内にあった酒造所がうるま市石川に移転するタイミングで神村酒造に入社しました。
「世界には多くの銀行員がいるが、泡盛を広める人は100人もいないのでは?ならば、自分がその伝道師になろう」

中里さんは、先代社長の神村盛也さんのもとで泡盛造りを学び、現在では7代目社長として奥様やスタッフと泡盛の魅力を広める活動に尽力しています。
「伝統的酒造り」がユネスコに登録、海外からの注目も高まる
2024年12月には、泡盛を含む日本酒や本格焼酎など、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されました。ユネスコ登録を追い風に、泡盛の海外への輸出にも力を入れていきたいと中里さんは話します。
「海外のバイヤーから商談の依頼も増えており、 日本の酒造りが注目されていることは確かです。海外で泡盛の評価が高まることで、国内や県内で泡盛の魅力が再認識されることも期待できます。また私達メーカーだけでなく、 飲食店やお土産品店などの関連業界にも良い影響がつながっていくと嬉しいですね」
国内外への泡盛の展開に、中里さんは「やれることはたくさんある」と力強く語ってくれました。
泡盛はみんなでワイワイ飲む楽しいお酒
泡盛造りの技術や文化が注目されるなかで、中里さんは泡盛の楽しみ方について話してくれました。
「ひとりでしっぽり飲むのも良いですが、どちらかというと泡盛は、家族や仲間とワイワイ飲む楽しいお酒です。温かいコミュニケーションを生む引き立て役として泡盛を飲んでもらえると、造り手としては胸がいっぱいになりますね」
泡盛はキツイというイメージがある方は、水割りやソーダ割り、フルーツと合わせてカクテルにアレンジするなど、さまざまな飲み方を試してみるのもおすすめです。
自分に合った飲み方を見つけると、泡盛のファンになる方も多い。そんな方を増やすために、中里さんはこれからも泡盛の魅力を発信し続けたいと話してくれました。
会社情報
会社名:有限会社 神村酒造
所在地:沖縄県うるま市石川嘉手苅570番地
アクセス:石川ICから車で5分(県道6号線沿)
電話:098-964-7628
※商品に関するお問い合わせは、0120-841-628まで(9:30~17:00 日曜休)
お問い合わせメール:info@kamimura-shuzo.co.jp
公式HP:https://kamimura-shuzo.co.jp/
公式Instagram:https://www.instagram.com/kamimurashuzo/
公式YouTube:https://www.youtube.com/@kamimurashuzo