山の斜面を背景に等間隔に並ぶ石地蔵の列。緩やかに波の曲線を描く小径は、わずか100mにも満たないミニマムな聖地です。

鮮烈な赤の列
赤い頭巾とよだれ掛け。赤には古来魔除け、厄除けの意が込められるといいます。その揃いの衣装で並ぶ88体の石地蔵。そこにはひとつとして同じ顔はありません。座像、立像、舟形地蔵(背景が船形の造形)、幼子の姿や複数の顔、手を持つものなど姿もさまざまです。
この印象的な景観は、安芸高田市吉田町、国の史跡の郡山(こおりやま)城跡の一角にあります。すぐ横には弘法大師を祀る『大師堂』も。
郡山は、戦国武将毛利元就が居城し生涯を閉じた場所として知られています。その元就が郡山に入城したのは大永3(1523)年。88体の石地蔵がこの山腹に据えられたのは天保年間(1830-1844)のことです。
むかし戦国武士の鎧道は、時が流れて江戸の庶民の拠り所であったのか。同じ山を舞台に、もうひとつの魅力(物語)がここにあります。



ご利益は四国巡礼と同等
なぜ、88地蔵が据えられたのか、どうして郡山だったのか、どのような意思決定があったのか、予算、工期、制作者など、詳細は不明です。
調べられる範囲で分かったことは、地元の郷土史『高田郡史・上』『高田郡史・民族編』ほか、古い資料の記述によると、中世から近世にかけて全国的に一種の巡礼や旅ブームがあり、その流行に乗って、もっと身近に四国八十八か所巡拝を行えるよう、大勢の信者らの厚志により地蔵の建立が叶ったとあります。
当時の世相は世界的に寒冷な時期(小氷期)で、日本では天保の大飢饉が起こりました。困難、悲惨な状況のなかで、地蔵は当時の人々の拠り所だったのかもしれません。
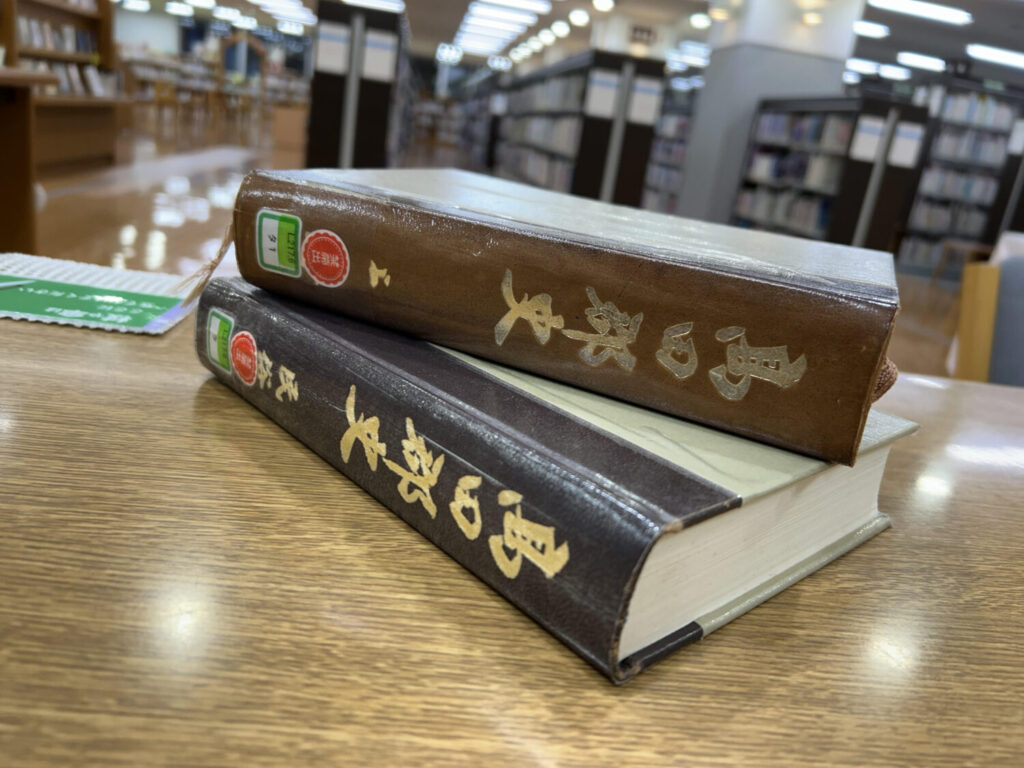
時代に翻弄される石地蔵
文久3(1863)年、郡山山麓の現吉田高校一帯に、広島浅野藩の陣屋『御本館(ごほんかん)』が築かれることになりました。「屋敷を見下ろす」との理由で88地蔵と大師堂は町内の青山の『大日堂』へ移転させられます。後に、明治44(1911)年、荒廃した様子が危惧され再び郡山へと戻されたのでした。
また、この辺りには地蔵にまつわる古い風習がありました。「祝いこみ」といわれ、婚礼の晩、賑やかに花嫁を迎える祝賀イベントです。
祝宴に座る花嫁の前や、その家の前に地蔵を担ぎ並べ「家に落ち着くように」と願掛けをしたそうです。地蔵がたくさん並ぶことは喜ばしいことでしたが、それらを元の場所に戻すのは祝われた側でした。
祝いこみに使用される地蔵は、88地蔵のほか町内の寺などから借り出されることもありました。しかし、首が落ちたり本体に傷がついたり欠けたりして、次第に完全な姿のものはなくなっていき、ついには警察が止めにし、大正中期には地蔵を使用する祝いこみはなくなったと記録にあります。



心惹かれる、もう3体
さて、88地蔵を1番から数えて歩くと、末尾88番の隣に小さなコロンとまあるい頭の地蔵があります。地蔵とはいえ顔は彫られていないし、明らかに88地蔵とは異なる作り。苔が張り付いた自然石の上に、角丸で窪みと厚みのある四角い台座に座る地蔵。なんとも愛らしい。いつの時代かのどなたかが、大事な誰かを想い独自に丁寧にこしらえて、この場所に大切に据えられたのではないだろうか。勝手な想像にしか過ぎないけれど、優しく切ない人の情が可視化された姿に思えてしまいます。
この小さな地蔵から少しだけ上に折り返すように登った場所に、いつから存在するのか、大小2体の地蔵があります。小さい方は台座から外れてしまっていますが、そのために隣の地蔵との間に支えられるような形で立っています。88地蔵に背を向けるよう、やや西北西を向く姿。この方角に、もしかしたら地蔵を安置した人の想いがあるのかも知れません。
ただ穏やかに、移る時代を見つめ続ける地蔵たちは、今日も静かに令和の吉田町を眺めています。地蔵が見てきた時間を心の中で借りながら、ミニマムなお遍路巡拝をしてみてはいかがでしょうか。4月の桜の時期も間近。88地蔵そばの郡山公園は桜の名所としても有名です。


基本情報
⚫️郡山城跡
広島県安芸高田市吉田町吉田
○バス=広島バスセンターから吉田出張所行き(約1時間25分)、安芸高田市役所前下車徒歩5分
○自動車=中国自動車道高田インターから20分
○JR=芸備線向原駅からタクシー20分
※向原駅から吉田へのバスは、日・祝休。平日・土曜は運行。ただし便数が少ないです。
⚫️安芸高田市歴史民族博物館
広島県安芸高田市吉田町吉田278-1
TEL 0826-42-0070
⚫️安芸高田市立図書館
広島県安芸高田市吉田町吉田761
TEL 0826-42-2421




