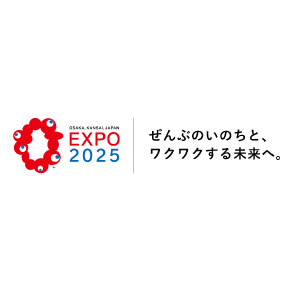大阪・関西万博のテーマ事業「いのちを高める」の一つとして誕生した『クラゲ館』は、すべての人の「つくるよろこび」を応援してくれる、やさしくてユニークな“遊び場”です。
アートに詳しくなくても、創造的なことに触れていない毎日でも、ここに来ればきっと気づくはず。「表現するって、楽しいんだ」「アートって、わたしの中にもあるんだ」──そんな気づきが、親子の心をふんわりとひらいてくれます。
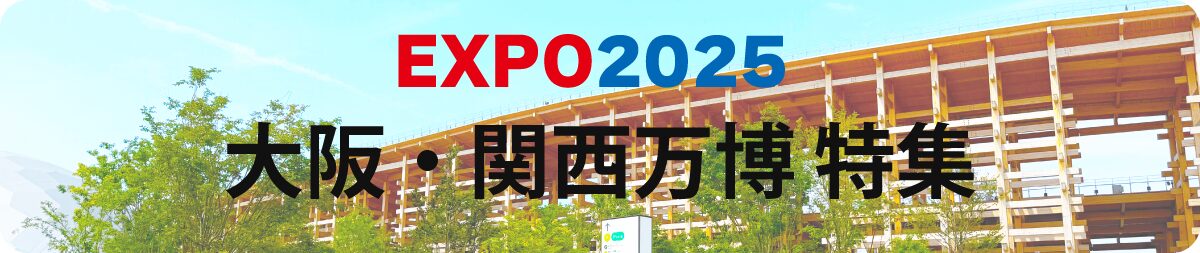
小さな冒険のはじまり。「プレイマウンテン」で子ども心にかえる

クラゲ館の入り口は、地上エリアへと続くやさしい丘「プレイマウンテン」。ここでは、まるで絵本の中に迷い込んだような体験が待っています。
風に揺れて音が鳴る《振るーと》は、にょろっと生えているようなユニークな形。手で優しく触れると、鈴のような音がチリンと響きます。

そして、丘の途中には、焼き物のタイルに水が流れ落ちる《土と水のカーテン》があります。
越前・瀬戸・常滑など日本を代表する六古窯のタイルが使われていて、水の揺らぎが涼しげな雰囲気を運んできてくれます。このカーテンのタイルには、展示制作に参加した子どもたちのサインが隠されているそうです(※水には入らないようご注意ください)。
地上エリア「いのちのゆらぎ場」で自由に遊び、音と光にふれる

クラゲ館の中心となる地上エリア「いのちのゆらぎ場」は、まるで半屋外の公園のよう。天候に左右されず、ルールいらずで、感覚のままに遊べる場所です。
中央には、たくさんの木材から作られた《創造の木》がそびえています。そのすぐ近くにあるのが、視界にふわりと広がる《ミドルクラゲ 海月(うみつき)》です。

ペットボトルのごみで作られたこのアート作品には、制作に参加した人たちの夢やメッセージが記されています。色とりどりの布が波のように垂れ下がり、光を受けてやさしく輝く姿は、まるで空を泳ぐクラゲのよう。

《音触(おんしょく)》は、ぷにぷにとしたゲルを押すと音や光が生まれる不思議な楽器。《角命(かくめい)》は、手をかざすと模様と音が変わる、アートと数学が融合した展示です。
ARカメラで遊ぶ《ごちゃまぜオーケストラ》では、動物や楽器のカードをかざすと、モニターの中で楽しい音楽セッションが始まります。

そのほかにも、病院で過ごす子どもたちが描いた900体のクラゲがピアノを彩る《希望のピアノ》、古いパソコンの部品を生かした《転生オルガン》、武器から生まれ変わった《武器アート》など、「いのちをつなぐ」展示が多数そろっています。

世界中の子どもたちが想いを込めて作ったタイルでできた《よろこびの壁》も、ぜひ近くで見てみてくださいね。ARを使うと、クラゲや動画が浮かび上がる楽しい仕掛けもあります。
地下エリア「いのちの根っこ」で、自分の中の“ひらき”と出会う
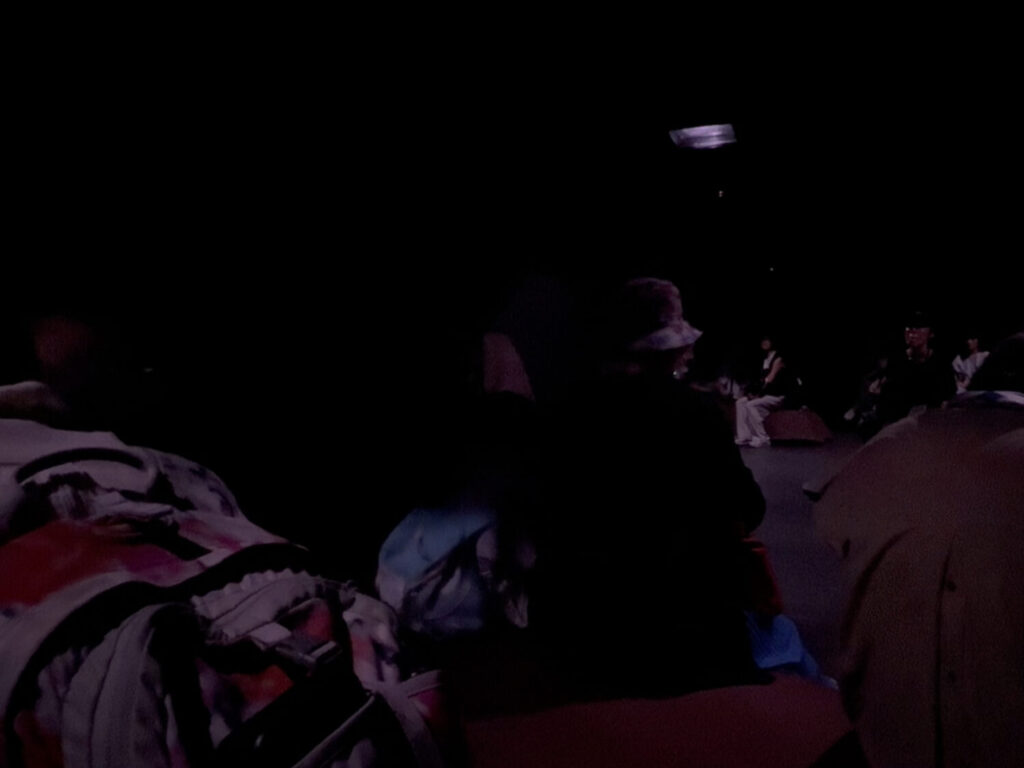
予約が必要な地下エリア「いのちの根っこ」では、少し照明を落とした静かな空間の中で、自分自身と向き合うような時間が過ごせます。
最初に体験するのは《わたしを聴く》。ここでは、森の音や焚き火の音、風、水中の音、さらには動物の鳴き声まで、世界中の自然音に全身が包まれます。目を閉じて、あちこちから聞こえてくる音に耳を澄ませてみてください。

そして、続く《わたしを祝う》では、雰囲気が一変します。立ったまま体験するこの空間では、最初に美しいピアノや笛の音が静かに響き、光が広がるような映像が360度スクリーンに映し出されます。幻想的な雰囲気のなかには、世界各地の仮面の姿も登場し、万物に宿る“いのち”を感じさせてくれます。
この空間には、常時2名以上の音楽家が登場。ピアノや笛などを使い、「いのちの旅」(作曲:中島さち子)にのせて即興で生演奏が行われます。映像と音がその場で重なり合い、“いまここ”でしか生まれない祝祭の空間がつくり出されていくのです。

しばらくすると音楽はだんだん力強くなり、画面には世界のお祭りの風景が現れます。すると、会場にいる人たちが自然と歩き出し、空間をぐるぐると巡り始めます。それはまるで、自分自身が祝福のパレードに参加しているよう。音と映像と動きがひとつになり、いのちの喜びが会場いっぱいに広がっていきます。
あそぶこと、表現することは、誰にとっても自然なこと

「つくる喜びをすべての人に!〜創造性の民主化〜」をテーマに、STEAM教育やアート活動を幅広く行っている中島さん。
クラゲ館は「表現することがこわい」「アートってよくわからない」という方にも、体験していただきたい場所です。小さなお子さんでも、難しい知識や使い方がわからなくても感覚的に楽しめて、アートや創造性にふれるきっかけになります。
そして、クラゲ館では万博閉幕まで、予約不要(先着順)で楽しめるワークショップやイベントも多数開催中です。ぜひ、クラゲ館の公式サイトで最新情報をチェックしてみてくださいね!
◆大阪・関西万博 いのちの遊び場 クラゲ館 (公式サイト)
※ワークショップとイベントのお知らせページはこちらです。