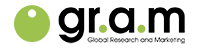学びながら旅をする。学んでから旅をする。
そんなスタディツーリズムの一環で、和歌山県が誇る世界遺産とフルーツの町「かつらぎ町」について一緒に学びませんか。
前回、お話いただいたのは、かつらぎ町出身、関東学院大学経済学部 中泉拓也教授。今回「かつらぎ学」を担当いただくのは、かつらぎ町出身の出版プロデューサー、木村隆さん。最近では10万部突破、船ケ山哲さん著「捨てられた僕と母猫と奇跡」といったベストセラー本のプロデュースを手掛けながら、かつらぎ町の広報アドバイザーを務めている方です。その木村さんに案内してもらったのは、西行法師ゆかりの地でした。
かつらぎ町とは
かつらぎ町は、北に和泉山脈、南に紀伊山地を望む風光明媚な土地で、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、農業が基幹産業となっています。柿をはじめとする果樹栽培が盛んで、フルーツ王国として知られています。一方で、食料品や繊維製造業など地場産業も発達しています。また、アニメ「君の名は」のモデルとなった町役場や、世界遺産の丹生都比売神社など、観光資源も豊富です。自然の恵み、歴史と文化、産業が調和した、味覚と心の体験が楽しめる魅力的な町なのです。
スタディツーリズムで和歌山県かつらぎ町の魅力を発見
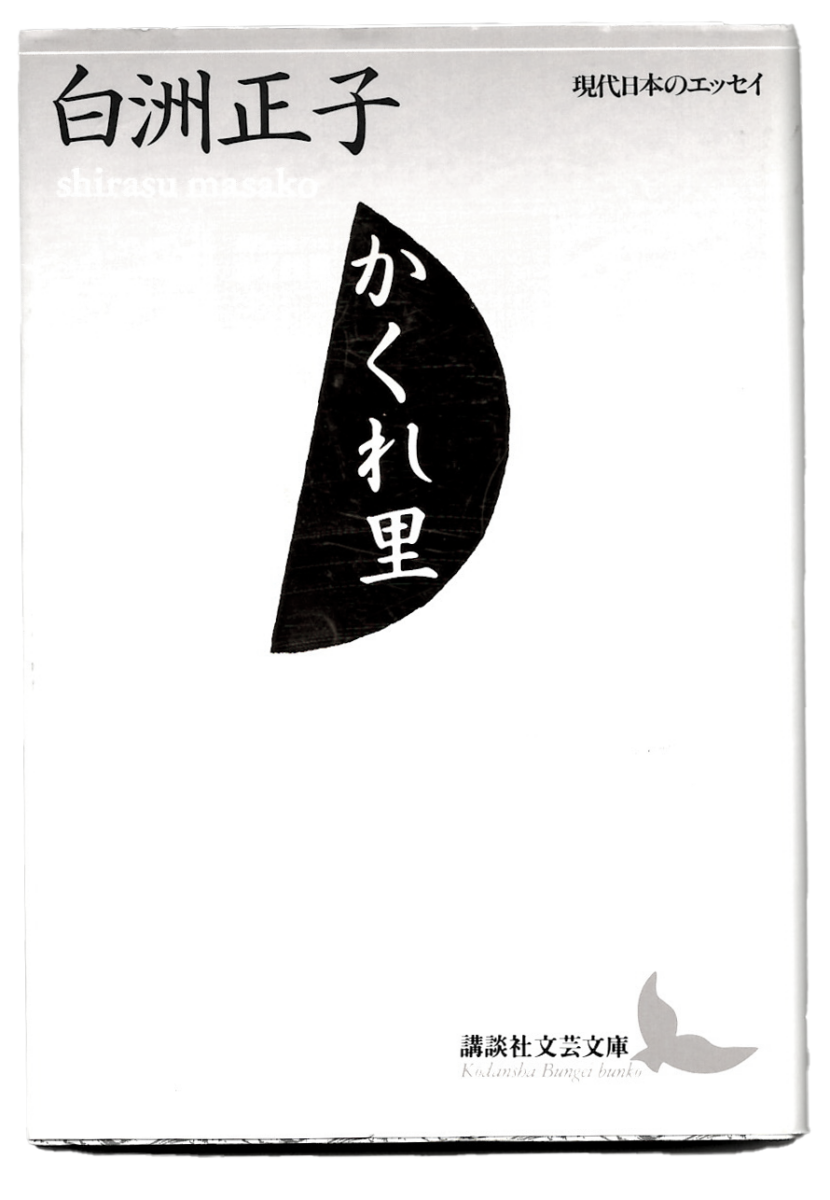
かつらぎ町を学びながら旅するなら「この本!!」ということで、木村さんから薦められたのは随筆家、白洲正子の「かくれ里」というエッセイ本。以下はその中の一節です。
周囲をあまり高くない、美しい姿の山でかこまれ、その懐ろに抱かれて天野の村は眠っていた。ずい分方々に旅をしたが、こんなに閑かで、うっとりするような山村を私は知らない。神社はその広々とした野べの、一番奥まった所に建っており、朱塗りの反橋の向こうに、大きな杉にかこまれて、どっしりした楼門が見えた時には、「来てよかった」と私たちは異口同音にいった
白洲正子は戦後、GHQとやりあったことで知られる、あの白洲次郎の妻。華族出身で、幼少時から能を習いながら、芸術全般への造詣を深めるとともに、旅人として各地を回られましたが、そのひとつとして、こよなく愛した地がかつらぎ町でした。
世界遺産 丹生都比売神社で体感する神秘的な参拝体験
かつらぎ町の魅力として、誰もが真っ先に挙げるのが世界遺産、丹生都比売神社(にうつめひめじんじゃ)。白洲正子も〈朱塗りの反橋の向こうに、大きな杉にかこまれて、どっしりした楼門が見えた時には、「来てよかった」〉と記述していますが、案内役になってくれた木村さんに従って、神社を訪れてみると、まさしく、その通りの感慨を抱かされます。


幻想的な光景に息を飲んでいると、木村さんは故郷のシンボルを前に、半世紀以上前の幼少時を振り返ります。
「僕たち、地元のこどもはね、丹生都比売神社と言わず、天野大社と言ってたかな。白洲正子が書いた通り、外鳥居から本殿までのアプローチがいいんだよね。歩を進めていくごとに心が洗われていくでしょう?」
たしかに、今、自分の身体が大地のエネルギーに包まれている、そんな不思議な感覚に襲われます。

木村さんからは、この丹生都比売大神は、古来魔除けとされる丹(赤)をつかさどり、あらゆる災厄を祓う女神だと教えていただきました。
この御神威(かむい)をもって、元寇を退け、以後、女神は神領高野山を弘法大師へ授けられ、高野山の総鎮守、真言密教の守護神になったということです。
これが神と仏が共にある、日本の祈りのすがたの源泉になったということなのですね。
参拝を終えると、木村さんの案内に従い、天野の村をまわってみました。

空気が、緑が、そして太陽がやさしい。それにしても、辺り一帯の景色がどことなく懐かしく思えるのは何故だろう?
幼少時から審美眼を鍛えてきた白洲正子がこの村のどこに魅了されたのかと考えると、やはり、この天野に日本の原風景を見出したのだろうと納得もしてしまいます。日本人が備える、内なる郷愁というものを自然とそそられるのかもしれません。
西行法師ゆかりの地で感じる歴史ロマンと白洲正子の足跡

「案内したいところがある、山を下りるよ」
そう促されて、木村さんが運転する車で向かったのは、公道から上がった小高い丘にある「西行堂」という庵でした。

「西行法師っているでしょう。その西行の妻と娘がここに住んでいたといわれている。西行がいた高野山は女人禁制だから、ここにとどまらざるを得なかった」
木村さんは西行堂の縁台に腰を下ろしながら、天野と西行法師との縁について話してくれました。西行の妻と娘はこの地に葬られ、小さな六地蔵が建てられているともいいます。
白洲正子もエッセイ「かくれ里」にこう記しています。
村の伝承では、西行は諸国を遍歴した後、高野山に住んでいたが、妻と娘が尼になって、天野へ移り住んだと聞き、いつしか山を下りて、晩年はこの草堂で暮した。おそらく伝説にすぎないが、晩年の彼には、行いすました高僧より、そういう姿を想像した方が似つかわしい

こうして、西行ゆかりの草堂は西行堂として、村人から祀られ、時がどれだけ流れても、再建は続けられ、平安時代から守り続けられてきたといいます。ちなみに現在のお堂は、昭和61年に場所を移して再建されたものとのこと。
木村さんは見晴らし良い丘から、天野の村を見下ろして呟きます。
「西行で有名なのがあるでしょう。仏には桜の花をたてまつれ、という句」
これは「もし自分を弔おうとする人がいるならば、仏さまに桜の花を供えてほしい」と西行が詠んだとされる代表作のこと。白洲正子はこの句をラストに持ち出して、エッセイ「かくれ里」に収めた「丹生都比売神社」の章を次の言葉で結んでいます。
私は、西行が晩年をここですごしたことを今はほとんど信じている。そういえば、神社のまわりには桜の木がたくさんあった。西行は吉野から高野への往復に、ここでも花を楽しんだに違いない。彼にはたしかに次のような歌があり、どういうわけか私には、ここ天野で詠んだような気がしてならないのである
仏にはさくらの花をたてまつれわがのちの世を人とぶらはば
かつらぎ町観光で楽しむ高野山参詣道と学習旅行の魅力
白洲正子を魅了した歴史ロマン。
ぜひ、彼女の本を片手に、かつらぎ町まで足を運び、悠久の時に想いを馳せてみてはいかがですか。
参考文献
「かくれ里」白洲正子 講談文芸文庫
かつらぎ町で夏祭り開催

開催日時:令和7年8月23日(土)午後5時00分~ ※荒天時は24日に順延
場 所:かつらぎ公園グラウンド(かつらぎ町大字丁ノ町)
内 容
ダンス等発表・盆踊り・打ち上げ花火・夜店
※ 打ち上げ花火の開始は、午後8時00分頃を予定しています。
(昨年より30分早い時間です)
詳細:https://www.town.katsuragi.wakayama.jp/040/010/020/2024-0606-1301-18.html